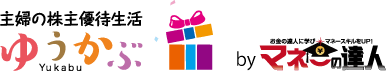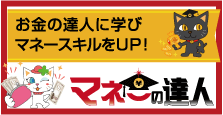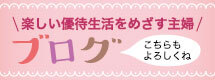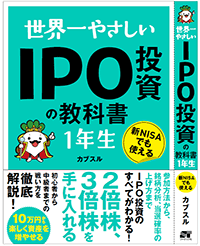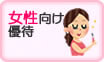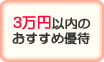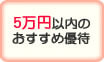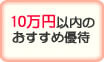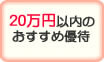- 現金6千円がもらえる お得なタイアップ企画を開催中♪
- 人気IPOに 当選しました!
株主優待のメリット
.png)
株主優待は、企業が株主に対して提供する特典で、投資初心者にも魅力的な要素がたくさんあります。
ここでは「株主優待のメリット」について、具体例を交えながら、株主優待がどのように投資初心者にとって有益であるのかを分かりやすく説明していきます。
優待投資では、商品やサービスの割引が得られたり、企業との繋がりを感じられます。
さらに、株主優待は配当とは別の利益で、税金の軽減も期待できます。
また、優待株は株価の下落に強い特性があり、長期保有で優待内容が豪華になる銘柄も存在します。
ただし、投資にはリスクが伴うため、リスクとリターンのバランスを考慮しながら、自分に適した投資を選択しましょう。
ぜひ、株主優待の魅力を知り、賢い投資を始めてみましょう。
目次
初心者も挑戦しやすい株主優待のメリット
株主優待のメリットを9つご紹介します。
1. 商品やサービスの提供・優待割引

株主優待の一番の魅力は、株を持っているだけで企業が提供する商品やサービスを割引価格で利用できたり、特別な優待が受けられることです。
これにより、普段の生活をお得に楽しむことができます。
例:デパートの株主優待で、10%割引が受けられたり、コーヒーを扱う企業で株主限定のコーヒー粉セットをもらえたりします。
2. 配当とは別の利益
株主優待は、配当とは別の利益で、株主は両方を通じてリターンを享受できます。
例:ファストフードチェーンの株主優待で、無料クーポン券を受け取り、普段の食事に利用することで、現金でもらう配当とは別に利益を享受できます。

加えて、一般的に、株主優待のない銘柄では年3%の配当金が高配当とされますが、優待株には年3%を超える合計利回りの銘柄も多く存在します。
(合計利回りとは、配当金と株主優待の価値を合わせた、お得度を表す指標です。)
高い利回りは株価の下落リスクを抑え、投資額の早期回収が期待できるため、優待株は投資家にとって魅力的です。
3. 税金の軽減
現物の株主優待(商品やサービス券など)は、一定の金額以下であれば、税金が課せられません。

一方、配当金は、株式投資から得られる利益であり、所得税の対象となります。
日本では、配当金に対して20.315%の税率(所得税15.315%+住民税5%)が適用され、源泉徴収されることが一般的です。(2023年現在)
ですので、株主優待をもらうことで投資家の負担を軽くすることができます。
例:あるアパレル企業の株主優待で、商品券を受け取ることで、現金配当とは異なり源泉徴収税がかからず、税金の負担を軽くすることができます。
4. 優待株は購入のタイミングが把握しやすい
株式投資で初心者が悩むポイントのひとつは、「買い時のタイミング」です。間違ったタイミングの高値で購入すると、損失のリスクが高まります。
しかし、優待株は独自のリズムで動くことが多いため、初心者でも購入のタイミングを把握しやすくなります。
買いのタイミングについては、株主優待目当てで高値買いするリスク で詳しく説明します。
5. 優待株は株価が下落しづらい!
株主優待を提供している企業は、提供していない企業に比べて、「株価が下落に強い」という特性があります。
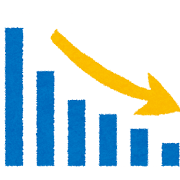
優待株を購入する投資家は、株主優待目的で購入することも多いため、優待を受け取るまで売らない人が多いのです。
株価の下落に強い企業は、損失リスクを減らすことができます。
6.長期保有で優待特典がアップする銘柄
長期保有することで優待内容が豪華になる銘柄があります。
優待が豪華になると利回りも向上し、長期保有にすることで日々の株価変動に悩まされず、気持ちに余裕が生まれます。
最近は長期保有する株主に特典を提供する企業が増えているので、好きな銘柄を見つけて長期保有するとお得感が高まります。
例:家電量販店の ビックカメラ(3048)は、年間3,000円分のお買い物優待券をもらえます。1年以上の長期保有で1,000円券1枚追加。2年以上で1,000円券が2枚追加されます。
7. 企業との繋がりを感じる
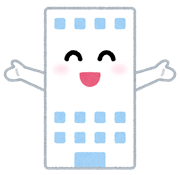
株主優待を受け取ることで、自分がその企業の一部を所有しているという実感が持てます。
企業の成長や活動に関心を持ち、応援したいと思えるでしょう。
例:ある飲料メーカーの株主優待を受け取ったとき、自分がその企業の一部を所有していると実感し、その企業の新製品やニュースに関心を持つようになります。
8. 投資家のロイヤリティを高める

株主優待を提供する企業は、投資家のロイヤリティを高めることができます。
投資家はその企業に対する信頼や愛着を持ち、長期的な取引を続けることが期待されます。
このことは企業だけではなく、投資家にもメリットがあると言えます。
ロイヤリティが高まることで、投資家にとっても、企業の将来の成長や成功に対する信頼感が高まり、安心して投資を継続できるという面があるからです。
例:スーパーマーケットチェーンが株主優待として割引クーポンを提供することで、投資家はそのスーパーで買い物を続けることが期待され、長期的な取引関係が築かれます。
9.株主優待は銀行預金よりお得!
優待投資は銀行に貯金するよりお得な選択肢として、投資初心者におすすめします。
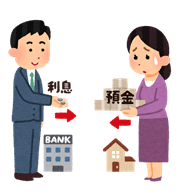
銀行の利息が低い現状では、優待投資で得られる利益や割引サービスが魅力的です。 優待投資を行うことで、配当金や株主優待の利益を享受し、長期的な資産形成に役立てることが可能です。
さらに、優待株は株価の下落に強い特性があるため、安定した投資が期待できます。
ただし、銀行と違って投資にはリスクが伴うため、自分に適した投資を選択し、リスク管理をしっかり行いましょう。
株主優待株投資のデメリット
株主優待投資のデメリットもいくつか存在します。
- 株主優待投資では業績や株価変動への注目が薄れ、リスク管理が十分できなくなることがある。
- 多くの企業に投資するとポートフォリオが散漫になり、資産管理が難しくなることがある。
- 株主優待の価値が期待通りでない場合もあり、満足度が低くなることがある。
- 優待株には配当金が少ない、もしくはない場合があるので、配当を確認することが重要。
- 配当金予算確保のために優待を廃止する企業もあり、株価急落のリスクがあるため、業績チェックが必要。
株主優待投資にはメリットがありますが、デメリットも理解し、バランスの良い投資判断を行うことが重要です。
[まとめ]
株主優待は投資初心者に魅力的なメリットが9つあります。
- 1. 商品やサービスの提供・優待割引
- 2. 配当とは別の利益
- 3. 税金の軽減
- 4. 優待株は購入のタイミングが把握しやすい
- 5. 優待株は株価が下落しづらい!
- 6.長期保有で優待特典がアップする銘柄
- 7. 企業との繋がりを感じる
- 8. 投資家のロイヤリティを高める
- 9.株主優待は銀行預金よりお得!
ただし、デメリットも理解し、リスク管理や資産バランスに注意して投資しましょう。

当サイトで提供している株主優待などの情報につきましては、その情報の正確性を確約するものではありません。
サイト内の情報には万全を期して掲載しておりますが、情報が古い、または誤っている場合等もございます。
最新の株主優待、配当金等の情報は各企業のホームページや証券取引所の開示情報にてご確認下さい。
また、サイト内の株価、配当利回り等の指標につきましては最新情報を表示しているわけではありませんのでご注意下さい。